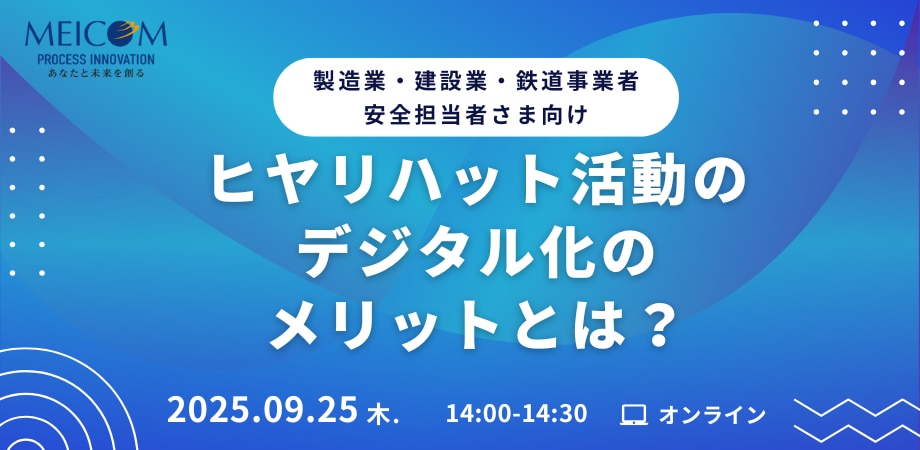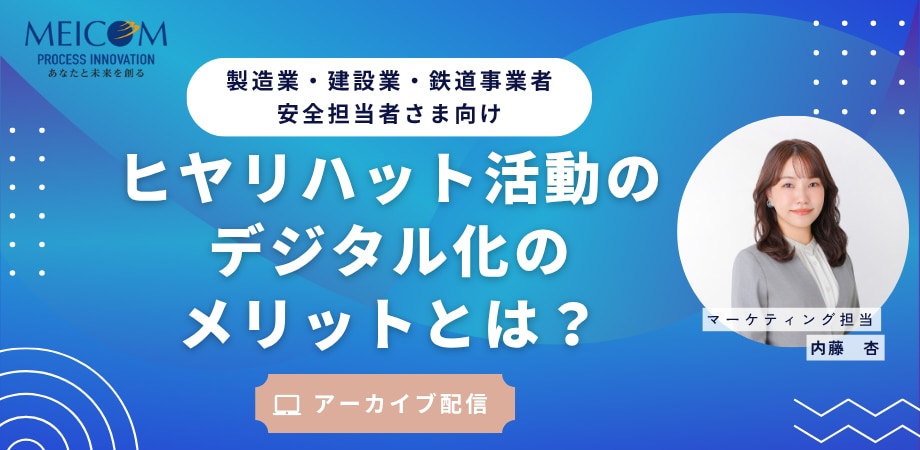労働災害を防ぐには?原因から防止策、法令知識まで徹底解説
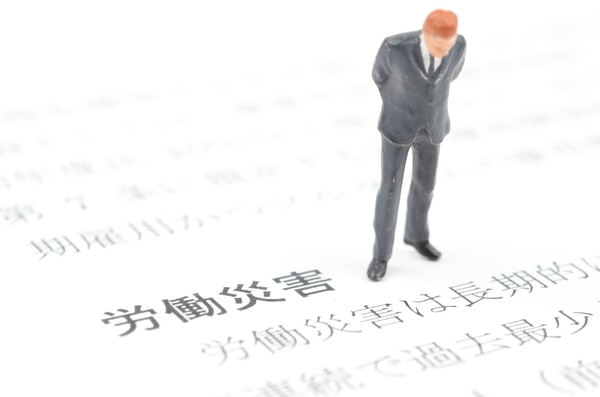
目次[非表示]
- 1.労働災害が発生する原因を詳しく解説
- 2.労働災害に関する法令知識と発生時の対処方法
- 2.1.労働安全衛生法
- 2.2.労働者災害補償保険法
- 2.3.発生時の対処方法
- 3.会社が労働災害を減らすためにできる防止策
- 3.1.転落災害の防止策
- 3.2.落下物災害の防止策
- 3.3.中毒・火災の防止策
- 3.4.熱中症の防止策
- 3.5.転倒の防止策
- 3.6.追突の防止策
- 3.7.はさまれ・巻き込まれの防止策
- 3.8.溺れの防止策
- 3.9.感電の防止策
- 3.10.交通事故の防止策
- 3.11.医療事故の防止策
- 3.12.利用者の事故の防止策(保育/介護現場)
- 3.13.システム障害・事故の防止策
- 4.労働災害を減らすために行政ができること
- 4.1.労働災害防止計画の推進
- 4.2.労働基準監督署の指導と監督
- 4.3.安全衛生教育の啓発
- 4.4.助成金制度の活用
- 5.労働災害を減らすために労働者ができること
- 5.1.安全手順を守る
- 5.2.保護具を適切に着用
- 5.3.体調を適切に管理
- 5.4.ヒヤリハットの報告
- 5.5.安全教育や訓練に積極参加
- 6.労働災害を防止するためにはヒヤリハット管理システムの活用を
- 6.1.ヒヤリハット管理システムの特徴
- 6.2.メイテツコムの「ヒヤリハットデータベース」のご紹介
- 6.3.導入のメリット
- 7.まとめ
労働災害は、労働者の安全と健康を脅かすだけでなく、企業の生産性や信頼性にも大きな影響を与えます。転落や感電、熱中症など、さまざまな形態で発生する労働災害ですが、その背景には共通した原因が潜んでいます。
本記事では、労働災害の原因を詳しく解説し、企業が取るべき具体的な防止策や法令知識、さらにはヒヤリハット管理システムを活用した予防策までを網羅的に紹介します。
この記事を読むことで、以下のメリットが得られます。
・労働災害の具体的な原因と防止策が分かる。
・労働災害に関する法令や行政の取り組みが理解できる。
・労働者が自分でできる安全確保の方法を知ることができる。
・ヒヤリハット管理システムを導入する意義が明確になる。
企業の安全管理者や現場責任者の方々にとって、労働災害防止に向けた第一歩となる内容をお届けします。
労働災害が発生する原因を詳しく解説

労働災害は偶然の出来事ではなく、明確な原因が存在します。その原因を理解し対策を講じることが、労働災害の発生を防ぐ第一歩です。
不安全行動
労働者自身の行動に起因するケースです。不安全行動の例としては以下のようなものがあります。
・安全装置の無効化:機械の安全装置を外したり、作業を効率化するために安全手順を無視する行為
・危険箇所への接近:注意喚起が行われている危険区域に立ち入る行動
・ヒューマンエラー:疲労や注意散漫による誤操作や判断ミス
不安全状態
作業環境や設備に起因する不備です。不安全状態の例は以下の通りです。
・施設の老朽化:機械や設備が劣化し、安全性が低下している。
・作業場の整理整頓不足:道具や材料が散乱しており、足元が滑りやすい状態
・照明不足や換気不良:視界が悪かったり、有害物質が充満する環境
管理上の問題
企業の安全管理体制に問題がある場合も、労働災害の発生につながります。
・安全教育の不足:従業員が適切な作業手順を知らない。
・管理体制の曖昧さ:現場での安全責任者が不明確で、指導が行き届かない。
・リスクアセスメントの未実施:作業のリスクが評価されておらず、危険が放置されている。
労働災害に関する法令知識と発生時の対処方法

労働災害を防止し、発生時に迅速に対応するためには、関連法令の理解が欠かせません。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るための基本的な法律です。この法律は、事業者に対して以下の義務を課しています。
・安全衛生管理体制の整備
・安全機器の設置と維持
・労働者への安全教育の実施
労働者災害補償保険法
この法律は、労働者が業務上の事故や疾病によって被害を受けた場合に、保険給付を提供します。例えば、療養費や休業補償給付、遺族給付が含まれます。
発生時の対処方法
労働災害が発生した場合、企業は速やかに以下の行動をとる必要があります。
1.応急処理:負傷者に適切な応急処置を施し、必要に応じて医療機関に搬送
2.労働基準監督署への報告:死亡や休業4日以上の災害は、所定の様式で速やかに報告
3.再発防止策の実施:災害の原因を分析し、再発を防ぐための具体的な改善策を講じます。
関連ウェビナーのご案内
労働災害の管理は、想定以上に手間がかかる一方で、いまだに紙やExcelなどのアナログ手法で運用している企業が多いのが現状です。
当社では、労働災害の前段階である「ヒヤリハット管理」をデジタル化することで、より効率的に労働災害対策を行える仕組みの活用を推奨しています。
デジタルツールを導入することで、情報共有の迅速化やデータ分析の容易化など、多くのメリットが得られます。
下記のウェビナーでは、ヒヤリハット管理のデジタル化に向けた具体的な方法を紹介しています(アーカイブ配信)。
ぜひご視聴ください。
会社が労働災害を減らすためにできる防止策

労働災害の多くは、適切な防止策を講じることで未然に防ぐことが可能です。ここでは、企業が取り組むべき具体的な防止策を13種類の災害・事故例に基づいて解説します。
転落災害の防止策
高所作業中の転落は、建設現場や工場で頻繁に発生します。
・安全帯や命綱の着用:作業者が高所でのバランスを崩しても安全を確保できるよう、全員に安全帯を着用させます。
・足場の点検と整備:足場の強度や安定性を定期的に確認し、不安定な箇所を改善します。
・安全教育の実施:作業前に危険箇所を共有し、高所での適切な動作を徹底指導します。
落下物災害の防止策
工具や資材の落下は、下方で作業する労働者に重大な危険をもたらします。
・ヘルメットの着用:全従業員にヘルメットを義務付け、落下物から頭部を保護します。
・工具や資材の固定:高所で使用する工具や資材は専用の固定器具を用いて安全に保持します。
・作業エリアの分離:落下物が発生する可能性のあるエリアを封鎖し、立ち入り禁止区域を設定します。
中毒・火災の防止策
化学物質の取り扱いや火気を伴う作業には特別な対策が必要です。
・有害物質の適切な保管:化学物質を規定通りの専用容器で保管し、取り扱いマニュアルを整備します。
・防火設備の設置:消火器や防火シャッターを設置し、火災時に迅速に対応できる体制を整えます。
・緊急時訓練の実施:火災発生時の避難ルートと行動を従業員に周知します。
熱中症の防止策
夏場の屋外作業や高温環境での作業は、熱中症のリスクを高めます。
・適切な水分補給:作業場に冷水やスポーツドリンクを配備し、定期的な水分補給を推奨します。
・作業時間の調整:気温の高い時間帯の作業を避け、作業時間を柔軟に変更します。
・休憩所の設置:涼しい休憩スペースを提供し、定期的に休息を取るよう指導します。
転倒の防止策
転倒事故は、整理整頓の不備や足元の障害物によって引き起こされます。
・床面の滑り止め加工:滑りやすい床には滑り止めシートや塗料を使用します。
・整理整頓の徹底:使用していない工具や材料を収納し、作業エリアを清潔に保ちます。
・適切な履物の着用:滑りにくい靴や作業靴を全員に支給します。
追突の防止策
車両や重機の追突事故は、運転ミスや注意不足が原因です。
・安全運転教育の実施:ドライバーに対して定期的な安全運転講習を実施します。
・速度管理の徹底:現場内では速度制限を設定し、違反がないよう監視します。
・車両の点検:定期的に車両や重機の整備点検を行い、不具合を早期に発見します。
はさまれ・巻き込まれの防止策
機械操作時に体の一部が挟まれたり巻き込まれる事故は、特に製造業で発生しやすいです。
・安全装置の設置:機械に非常停止ボタンや安全柵を設置し、危険箇所への接近を防ぎます。
・操作マニュアルの徹底:各機械の使用方法を従業員に熟知させ、誤操作を防ぎます。
・メンテナンス中の電源遮断:修理や清掃時には、必ず機械の電源を完全に遮断します。
溺れの防止策
水辺や水を扱う作業現場では、溺れるリスクがあります。
・ライフジャケットの使用:水に近い作業エリアではライフジャケットの着用を義務付けます。
・安全柵の設置:水際に安全柵を設置し、転落を防止します。
・監視体制の強化:水辺作業では監視員を配置し、緊急時の対応を迅速に行える体制を整えます。
感電の防止策
電気作業では、感電の危険性があります。
・絶縁工具の使用:作業員には絶縁性の高い工具を支給します。
・電源の遮断:作業前に必ず電源を遮断し、通電確認を行います。
・資格保持者の配置:電気工事士などの資格を有する者に作業を担当させます。
交通事故の防止策
業務中の移動や配送時に交通事故が発生することがあります。
・安全運転管理者の設置:運転者の健康状態や車両の使用状況を把握し、適切な指導を行います。
・ドラレコの導入:ドライブレコーダーを活用し、運転状況を記録・評価します。
・長時間運転の禁止:休憩を挟んだ運転計画を立て、疲労運転を防ぎます。
医療事故の防止策
医療現場では、さまざまな医療事故の可能性があります。
・チェックリストと二重確認の徹底:薬剤の投与や重要な医療手続きを行う際には、常に二人以上の医療従事者による確認を行います。
・教育と訓練の強化:シミュレーション訓練を行い、緊急事態に対応するスキルを向上させます。
・コミュニケーションの改善:チーム内でのコミュニケーションを強化し、情報の伝達ミスを防ぎます。
利用者の事故の防止策(保育/介護現場)
保育や介護現場では、転倒、誤嚥、怪我など、利用者が事故をしてしまう可能性があります。
・環境整備と安全対策:施設内外の環境を定期的に点検し、安全に配慮した設計や配置を行います。
・利用者の状態モニタリングと個別対応:利用者一人ひとりの健康状態や行動パターンを把握し、特に注意が必要な利用者には個別対応を行います。
・スタッフの教育と訓練:スタッフに対する定期的な教育と訓練を実施し、事故防止のための知識やスキルを向上させます。
システム障害・事故の防止策
システムの稼働を止めないために、下記の点に注意をする必要があります。
・定期的なバックアップとリカバリープランの確立:バックアップのテストやリカバリープランの演習を定期的に実施し、実際の障害時に確実に機能することを確認します。
・モニタリングとアラートシステムの導入:システムのパフォーマンスや稼働状況をリアルタイムで監視するモニタリングツール、および異常が発生した場合にアラートを発信し、関係者に通知する仕組みを整えます。
・定期的なセキュリティ対策の強化:セキュリティパッチの適用やウイルス対策ソフトの更新を徹底し、最新の脅威に対する防御を強化します。
労働災害を減らすために行政ができること

労働災害を未然に防ぐため、行政は法令の制定や指導を通じて多方面で対策を進めています。以下は具体的な取り組みです。
労働災害防止計画の推進
厚生労働省が策定する労働災害防止計画は、事業者に自主的な安全衛生活動を促すための基本指針となっています。この計画には、業種ごとの目標や対策が明確に示されており、事業者はこれに基づいて具体的な施策を講じます。
労働基準監督署の指導と監督
労働基準監督署は、事業場への立ち入り調査を行い、安全管理体制や法令順守状況を確認します。必要に応じて是正勧告を行い、労働環境の改善を促します。
安全衛生教育の啓発
行政は、事業者や労働者に対して安全衛生教育の重要性を訴え、適切な教育プログラムを提供しています。これにより、現場での安全意識を高め、災害発生率を低下させることを目指しています。
助成金制度の活用
行政は、中小企業が労働災害防止のための設備投資や安全管理体制の強化を行う際に、助成金を通じてサポートを行います。これにより、費用面での負担が軽減されます。
労働災害を減らすために労働者ができること

労働災害を未然に防ぐため、企業や行政だけでなく、労働者自身の取り組みも重要です。以下に労働者が行うべき対策を示します。
安全手順を守る
作業手順書やマニュアルに従い、規定通りに作業を進めることが最優先です。自己流のやり方は災害リスクを増大させます。
保護具を適切に着用
ヘルメット、安全靴、手袋などの保護具は、危険から身を守るために欠かせません。使用前には損傷がないか確認することも重要です。
体調を適切に管理
十分な休息をとり、健康状態を良好に保つことで、注意力の低下や判断ミスを防ぎます。また、体調不良時には無理をせず、休む選択も必要です。
ヒヤリハットの報告
自分や同僚が危険を感じた場面(ヒヤリハット)を積極的に報告することで、職場全体のリスクを低減できます。
安全教育や訓練に積極参加
会社が実施する安全教育プログラムに参加し、最新の安全対策や作業方法を学びます。
労働災害を防止するためにはヒヤリハット管理システムの活用を

ヒヤリハット事例の管理と活用は、労働災害防止において極めて効果的な方法です。ここでは、ヒヤリハット管理システムの活用方法とそのメリットを解説します。
ヒヤリハット管理は、いまだに紙やExcelなどのアナログ手法で運用している企業が多いのが現状です。
しかし、デジタルツールを活用することで、情報共有や分析の効率化など多くのメリットが得られます。下記のウェビナーでは、ヒヤリハット管理のデジタル化に向けた具体的な方法をご紹介しています。
30分のショートウェビナーですので、お気軽にぜひご視聴ください。
ヒヤリハット管理システムの特徴
ヒヤリハット管理システムは、現場でのヒヤリハット事例を効率的に収集・管理し、データの分析をすることで再発防止策を立案できるツールです。
メイテツコムの「ヒヤリハットデータベース」のご紹介
ヒヤリハットデータベースは、労働災害防止のために設計された高度な管理システムです。その主な特長は以下の通りです。
・簡単な登録機能:現場の労働者がスマートフォンやタブレットで直観的にヒヤリハットを報告
・強力な分析ツール:データを基に、リスクの原因と頻度を詳細に分析
・導入支援とサポート:専門スタッフがシステム導入から運用までをサポートし、効果的な活用を促進
導入のメリット
・事故発生率の低下:ヒヤリハットの活用により、未然に事故を防止
・従業員の安全意識向上:労働者が危険に気づき、報告する習慣を醸成
・導入支援とサポート:安全管理が徹底された企業として、社外評価が高まる。
詳細についてはコチラ↓
まとめ
労働災害は、企業や労働者が適切な対策を講じることで未然に防ぐことが可能です。
本記事では、労働災害の原因、法令知識、具体的な防止策、行政の取り組み、労働者自身の対策、そしてヒヤリハット管理システムの重要性について詳しく解説しました。特に、ヒヤリハット管理システムを活用することで、リスクを可視化し、労働災害を効率的に防止できます。企業の安全管理者の方々は、これらの知識を基に、自社の安全管理体制を強化し、安全で働きやすい職場環境を実現してください。
労働災害ゼロを目指し、まずは小さな一歩を踏み出しましょう。
これらの取り組みは、単に労働災害を防止するだけでなく、事業の継続性を確保し、企業の信頼性を高めるためにも極めて重要です。
企業の繁栄は、安全で健康な労働環境の上に成り立ちます。
従業員の安全を守ることが、事業の永続的な発展に繋がります。